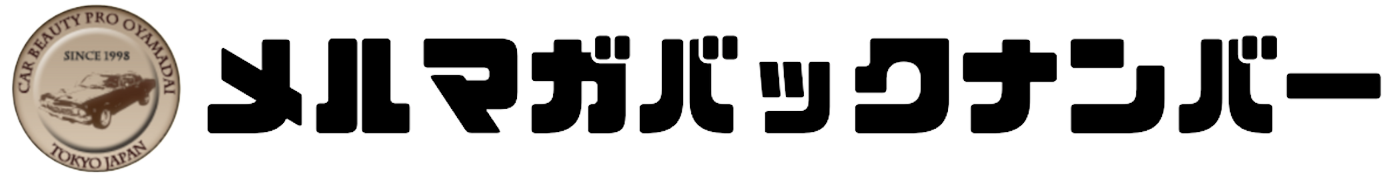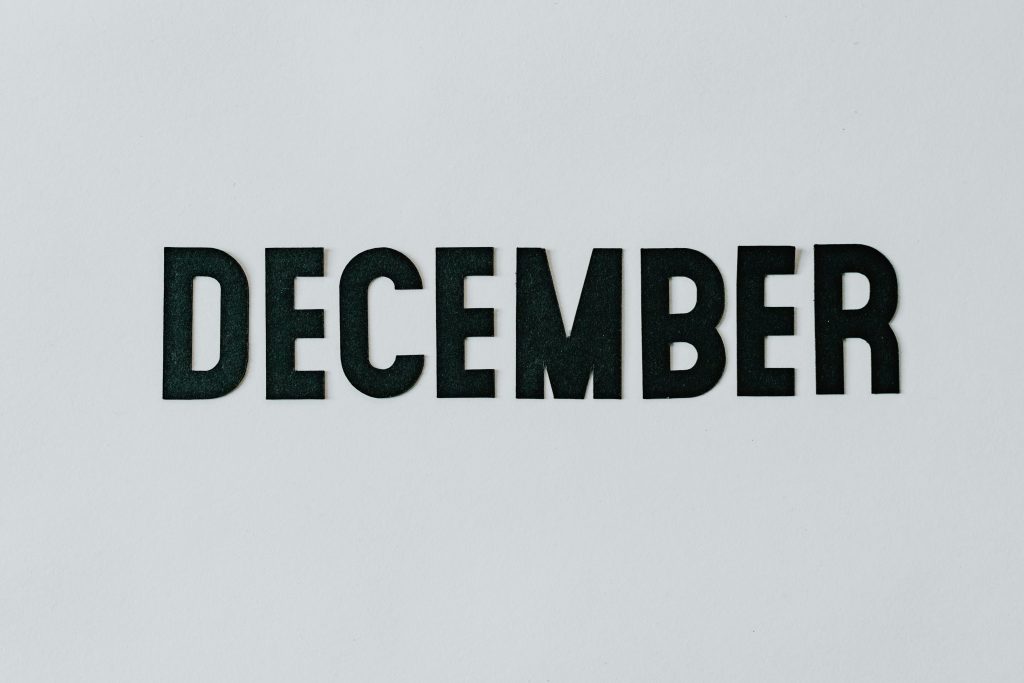-

高速道路の標識は、なぜ青にならなかったのか
今日のお話ですどうぞご覧ください 高速道路の標識は、なぜ青にならなかったのか 隔週の日曜日は奇跡でも起きない限り東名高速の渋滞に巻き込まれています そして、動かない車列の中でぼんやりと前方を眺めているとふと“当たり前すぎて気にも留めなかった... -

師走 その2
今日のお話ですどうぞご覧ください 師走 その2 本日、12月12日は「バッテリーの日」ですこの記念日は日本蓄電池工業会(現・電池工業会)が1985年(昭和60年)に「カーバッテリーの日」として制定し1991年(平成3年)に「バッテリーの日」へと名称を変更... -

師走
今日のお話ですどうぞご覧ください 師走 気づけばもう12月11日です朝の空気は一段と冷たく「あぁ、冬なんだな」と思わされますが空気の密度が濃く、酸素量が多いせいか私の燃焼効率も上がり絶好調です 師走第一週の作業 MercedesBenz CLS200DエシュロンNA... -

技の家系の小さな工場から始まったお話 7
今日のお話ですどうぞご覧ください 技の家系の小さな工場から始まったお話 7 日曜日の公園でベンチに腰を下ろしボーっとしているとボール遊びをしている女の子が伊部さんの目に入りました ボールは落ちても壊れず何度も弾んで戻ってきます その様子を眺め... -

技の家系の小さな工場から始まったお話 6
今日のお話ですどうぞご覧ください 技の家系の小さな工場から始まったお話 6 基礎実験すら完了していない伊部さんに残された時間は、あと6ヶ月 そんな中、実験を続けている伊部さんのもとへデザイナーが声をかけました「伊部さん、商品名を考えました!重... -

技の家系の小さな工場から始まったお話 5
今日のお話ですどうぞご覧ください 技の家系の小さな工場から始まったお話 5 伊部さんはインタビューの中で「エンジニアとしては唯一作りたい」と仰っていました 社内ではすでに「基礎実験は済んでいる」ことになっていたため 伊部さんはひっそりと試作を... -

技の家系の小さな工場から始まったお話 4
今日のお話ですどうぞご覧ください 技の家系の小さな工場から始まったお話 4 1981年「新技術、新商品提案書」に書かれたたった一行の文章から、すべては始まります その文章を書いたのはカシオの若手技術者 伊部菊雄(いべ・きくお) その文章とは「落とし... -

技の家系の小さな工場から始まったお話 3
今日のお話ですどうぞご覧ください 技の家系の小さな工場から始まったお話 3 1957年6月樫尾四兄弟が改良を重ねて完成させた 純電子式卓上計算機「14-A」が正式に商品化されます 歯車もモーターも使わず電気信号だけで計算を行いそれは世界で初めて “完全電... -

技の家系の小さな工場から始まったお話 2
今日のお話ですどうぞご覧ください 技の家系の小さな工場から始まったお話 2 カシオといえば電卓と腕時計のイメージが強いですが実はそれだけではありません 写真の世界ではデジタルカメラ(QV-10/EXILIM) を生み 音の世界では 電子キーボード、電子ピア... -

技の家系の小さな工場から始まったお話
今日のお話ですどうぞご覧ください 技の家系の小さな工場から始まったお話 1917年いまの高知県南国市、当時の久礼田村でのちに、自分の技で生きていく青年が誕生しました 「樫尾忠雄(かしお ただお)」 忠雄は高等小学校を出ると見習いの旋盤工として働き... -

見えない世界
今日のお話ですどうぞご覧ください 見えない世界 子どもの頃や青春時代に憧れたり欲しかったモノ、大切にしていたモノは大人になると懐かしく思えたり実際に手にしたり年齢を重ねてもあの頃の気持ちだけは不思議と色褪せません そんなことを考えていた矢先... -

忙しい中での今月の楽しみ
今日のお話ですどうぞご覧ください 忙しい中での今月の楽しみ 今月、いや今年一年を通しての楽しみは12月19日前後に 3I/ATLAS が再び接近することです NASA(アメリカ航空宇宙局)ESA(欧州宇宙機関)をはじめ世界中の観測機関がこの星を追っています 人...