今日のお話です
どうぞご覧ください
電気に生かされる私たち その9
ヴォルタ電堆(世界初の電池)までをまとめると
紀元前 静電気という「現象」
2600年前、タレスが琥珀をこすり
軽い物が引き寄せられる現象を記録
これが“電気”に関する最古の記述です
1600年 電気が「科学の言葉」に
ギルバートが electricus と名づけ
初めて電気が科学として扱われはじめる
1663年 人工的に電気を作る
ゲーリケが世界初の摩擦起電器を発明し
人類が“電気を作る”ことに成功
1700年代 強い静電気を発生できるように
ホークスビーらが改良し
人工の雷の研究が一気に進む
1745年 電気をためる技術が登場
ライデン瓶(世界初の蓄電器)が誕生
電気を“ためる”という革命的発見
1752年 雷=電気 を証明
フランクリンの凧実験によって
雷が巨大な静電気であることが確定
1771〜1791年 生体電気の発見
ガルバーニが「生命は電気で動く」ことを示し
神経・筋肉・心臓・脳の仕組みの
核心が明らかに
1800年 世界初の電池(文明の始動)
ヴォルタがガルバーニとの論争を経て
ヴォルタ電堆(世界初の電池)を発明
人類は初めて “途切れない電流” を手に入れる
これまで電気の歴史を書いてきましたが
乗り物好きとしては「乗り物と電気」のことを
触れないわけにはいきません
では、人類が最初に
“自動で走る”ことに成功した
乗り物は何でしょう?
多くの方が
「最初の乗り物はガソリン車」
と思いがちですが、実は違います
人類が最初に動かしたの
はまったく別の動力でした
それは1769年、フランス
ニコラ=ジョゼフ・キュニョーが作った
蒸気を動力とする“三輪車”です
この1769年という年は
ガルバーニの生体電気発見(1771〜)よりも前
“生命は電気で動く”という概念すらない時代に
蒸気の力で車を動かしていたのです
この蒸気三輪車は
軍が大砲を運ぶために設計したもので
蒸気の圧力で人間の力なしに前へ進む
まさに人類初の「自走する車」
しかし技術はまだ未熟で
最高速度は 時速約4km
ブレーキという概念はなく
舵輪(ハンドル)も反応が鈍く
曲がるのも大変でした
そして 1771年
試験走行中に減速できず
車はそのまま 兵舎の石壁へ突っ込み
これが記録に残る
「世界初の自動車衝突事故」となります
現代のクルマなら
自動ブレーキやABSが当たり前ですが
最初の自動車は止まることすらできなく
それでも、この“時速4kmの暴走三輪車”が
すべての始まりになりました
出典:参考
キュニョーの蒸気三輪車(1769)
Archives Nationales de France(フランス国立公文書館)
Musée des Arts et Métiers(パリ:実車レプリカ展示)
Nicolas-Joseph Cugnot, “Fardier à vapeur”(1769)
世界初の自走する車、世界初の自動車事故(1771)
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
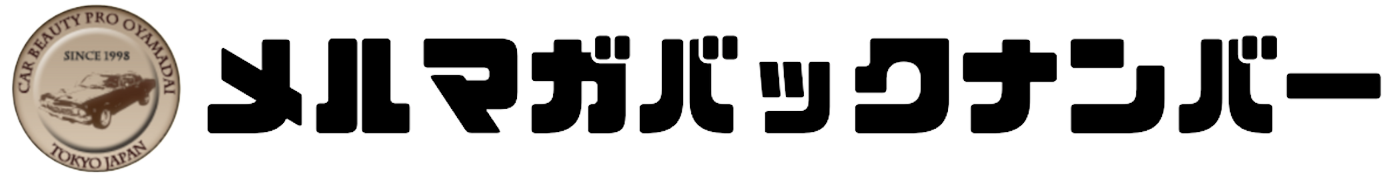
コメント