今日のお話です
どうぞご覧ください
戦後の国産車は
そして1939年ヨーロッパで
第二次世界大戦が勃発
そして、ねじは二重構造
職人技が生んだ世界最高の精度の
零式艦上戦闘機(零戦)も
JES-A(ウィットウォースインチ系)
戦艦「大和」「武蔵」も
JES-A(ウィットウォース系インチ)で
一部にDINメートルが併用されていました
日本の技術の粋を集めたモノにでさえ
ねじはウィットウォース(インチ)と
ドイツ式メートル(DIN)の
双方が用いられていたのです
そして1945年
長く続いた戦争が終わり
造船所も航空機工場も停止
残された機械の多くは戦前のインチねじ(JES-A系)や
ドイツ式メートル(DIN系)が混在していました
その後、日本は連合国軍の管理下に置かれ
工業界も一時的にアメリカ式への転換を迫られます
戦時中まで使用されていた日本のJES-Aは
基本的にイギリス型を継承したものでしたが
占領軍を主導したアメリカではすでに
UNC/UNFというアメリカ独自の
インチ規格が使われており
戦後の占領政策により
日本国内の整備・補修機械にも
この規格が持ち込まれました
GHQは兵器解体・航空産業の一時禁止と同時に
各地の工場・造船所・自動車整備所を
「民需工業」として再稼働させ
その際、アメリカ軍が持ち込んだ
機械・工具・車両などは
すべてUNC/UNFねじで統一されていたため
整備を行うにはアメリカ規格の
工具・タップ・ダイスが必要となりました
こうして戦後の工場では
JESインチ、UNCインチ、DINメートルという
3つの規格が混在する状況になったのです
「このままでは復興もままならない」と
日本の製造業はこの状況を逆手に取り
アメリカの機械・規格・工具を徹底的に研究し
UNC/UNF互換部品の国産化を進めました
1949年、「JIS(日本工業規格)」誕生
アメリカの援助のもとで「JIS B 0206」などの
ねじ関連規格が正式に制定されます
インチ系ねじはUNC/UNF(米国統一規格)を採用
メートル系ねじはISO(国際標準化機構)準拠の
メートルねじ系を採用し
このとき日本は、世界でも珍しい
アメリカインチ+国際メートルの
二重体系を併存させた国家となりました
1950年代前半まで
自動車・造船・鉄道・通信などの再建工場では
GHQ経由で導入された機械の多くが
UNC/UNF仕様だったため
現場では「インチ工具」と「メートル工具」が
日常的に併用されていました
特に自動車分野では
アメリカ製トラック(ジープなど)の
整備を通じてインチ規格の部品文化が
根強く残る結果となり
日産DAトラック(1946年)
トヨペットSA型乗用車(1947年)など
日本の戦後初期の国産車は
実はUNC/UNFボルトで
組み立てられていたのです
また1955年発売の
トヨペットクラウン(RS型)や
日産オースチンA50ノックダウン車も
車体はインチ系国産部品はメートル系の混合でした
つづく
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
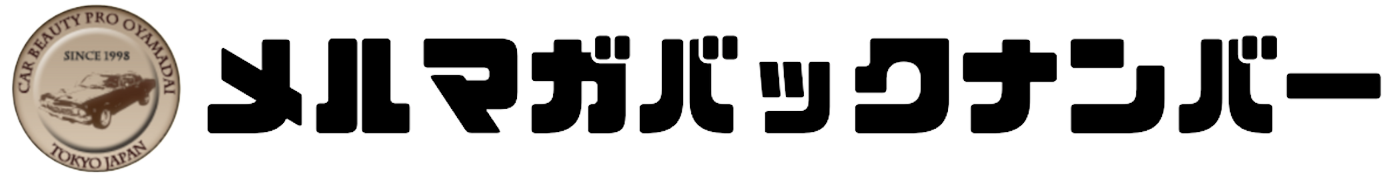
コメント