今日のお話です
どうぞご覧ください
初めてのねじ規格
1857年、佐賀藩の田中久重が
日本初の国産旋盤を完成させ
たのをきっかけに
日本は本格的に「ねじ製造」に
取り組み始めます
日本国内には佐賀藩が製作した国産旋盤と
幕府が長崎製鉄所に導入した
オランダ経由のイギリス製旋盤 の
二つの系統が存在していて
当時のオランダでは
イギリス製の工作機械が多く輸入され
それらはウィットウォース規格に
準じたねじを使用していました
一方、佐賀藩の旋盤は
オランダ製旋盤を手本にした
「手削り式の旋盤」で削り出されたねじは
一本ごとに寸法が異なる「固有ねじ」で
つまり、無規格のねじですので
同じ部品でも他の旋盤や機械には
合わなかったのです
その後も各藩では試行錯誤が続き手削りによるねじ製作が
行われていました
やがて時代は幕末から明治へ
開国とともに西洋の技術が一気に流入し
日本はイギリス・アメリカ・ドイツなどから
工作機械や兵器を次々と輸入しますが
ここで早くも新たな問題が浮上しました
「ねじが合わない」
それぞれの国で使われているねじの規格が
バラバラだったのです
この問題を解決するため明治初期の日本では
イギリス方式を統一基準として採用します
1870年の新橋〜横浜間の
鉄道建設をきっかけに横須賀造船所、長崎造船所
東京砲兵工廠など主要工場で
ウィットウォースねじ(BSW)が
実質的な標準として採用されました
翌1871年、工部省が設立されて
イギリス技術が国家的に導入されると
このウィットウォースねじが
日本における初めて採用された
国家レベルのねじ規格となります
なんと、日本が最初に導入したねじ規格は
イギリスのウィットウォースねじ(BSW)
つまり英国のインチ規格だったのです
初めてこの事実を知ったとき
私は少し驚きましたしかし、当時の時代背景や
世界の流れを考えれば
それはむしろ「自然な選択」
だったのかもしれません
やがて日本は
イギリスのウィットウォースねじをもとに
自国の産業構造に合った
独自のねじ規格を整備していきます
明治の近代化が進むなかで
各官営工場や軍需工場ごとに
ねじ寸法が異なり
「同じ1/4インチでも合わない」という
混乱が続いていました
この不統一を解消するため
1917年、商工省が中心となり
日本初の国家規格として
「日本標準規格(JES)」を制定しました
このJESは
イギリスのウィットウォース(BSW)を
基礎としながらも
日本の機械工作精度や製造技術に合わせて
寸法や公差を細かく調整した
いわば「日本版ウィットウォース」
と言えるものでした
その後、戦前の航空機・造船・鉄道など
あらゆる産業でJESねじが標準化され
現在は何も不自由なく安心して工具を購入し
そして「ねじを回している」私ですが
それは過去に多くの職人や技術者たちが
「合わないねじ」と格闘しながら
今の「標準化された便利さ」を
支える基盤を作ってくれたからこそ
成り立っているのだと思います
ねじの規格というのは
調べれば調べるほど面白く
気づけばどんどん深みに
ハマってしまいますので
次回でいったんこの話を締めたいと思います
出典・参考文献
『日本ねじ工業史』日本ねじ工業協会(1983)
工業技術院『JIS制定50年史』(1999)
日本産業技術史学会『日本のねじ産業発展史』
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
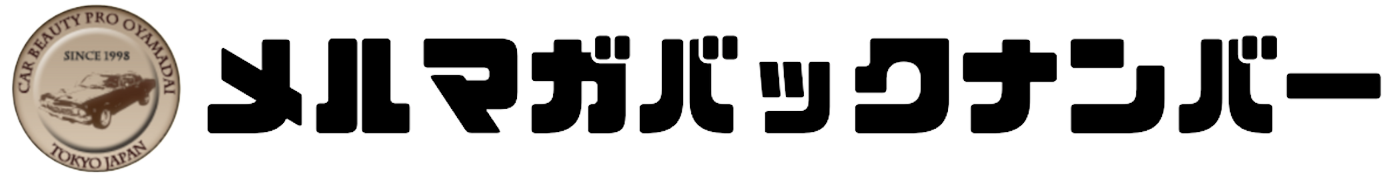
コメント