今日のお話です
どうぞご覧ください
日本人が初めて「ねじ」を回した日
実は、日本で「ねじ」が
初めて使われた時期は意外と古く
戦国時代(1543年・天文12年)まで
さかのぼります
それ以前の日本では
木造建築はすべて木組み
(ほぞ組・込み栓・楔〈くさび〉)
によって構築され城、寺院、神社
住居といった建築物にも
金属ねじは使われていませんでした
軽いもの、たとえば仏具や家具では
紐・縄・竹釘・木釘を使って固定し
金属製品では「ねじ」の代わりに
リベット(鋲)やかしめによ
る接合が用いられていました
刀の鍔(つば)や柄の固定、鎧・兜の接合
鉄製農具の柄付けなどがその代表例です
そして1543年、戦国時代の真っ只中
暴風に流された3人のポルトガル人が
鹿児島県の種子島に漂着しました
彼らが手にしていたのは
当時の日本人が見たことのない
金属製の武器、火縄銃でした
これが、日本人が初めて目にした
「ねじ付きの金属製品」だとされています
種子島の領主・種子島時尭(ときたか)は
その構造に驚き、火縄銃2挺を購入します
この銃に使われていた金属部品のうち
特に銃身の接合部(尾栓/bisen)には
ねじ構造が採用されている例が多く見られ
一方で、火皿(pan)は
ねじ止めのものもありますが
ヒンジ式やピン止め、嵌合による固定など
さまざまな方式が存在していました
この火縄銃を分解して構造を研究し
国産化に挑んだのが
種子島の鍛冶職人・八板金兵衛清定
(やいた きんべえ きよさだ)です
清定は火縄銃の模倣と
尾栓のねじ込み方式を再現し
約半年後に国産火縄銃の製造に
成功したと伝えられています
当時はもちろん「ねじの規格」もなく
火縄銃に使われたねじには
すり割り(マイナス)型のほか頭のない打込み式や
角棒で回すタイプ(スクエア型)など
さまざまな形状が見られました
また、旋盤やタップ・ダイスなどの
専用工具も存在しなかったため
職人たちは鑢(やすり)・鋸(のこぎり)
錐(きり)・ノミなどを使い一本ずつ手作業で
ねじ山を刻んでいたと考えられています
この技術はやがて鉄砲鍛冶を通じて
各地に伝わり
全国に「ねじ文化」が広がっていきました
それにしても八板金兵衛清定名前からしてすでに
「板金の神様」
になる運命だったのかもしれませんね
※八板金兵衛清定が火縄銃を再現する過程で
尾栓のねじ込み方式が実用化され
これが史料上で確認される
最古の日本製ねじの一例とされています
出典・参考文献
「鉄炮記」
火縄銃伝来および八板金兵衛清定の記述
「南蛮記」
ポルトガル人の種子島漂着に関する記録
日本産業技術史学会「日本のねじ産業発展史」
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
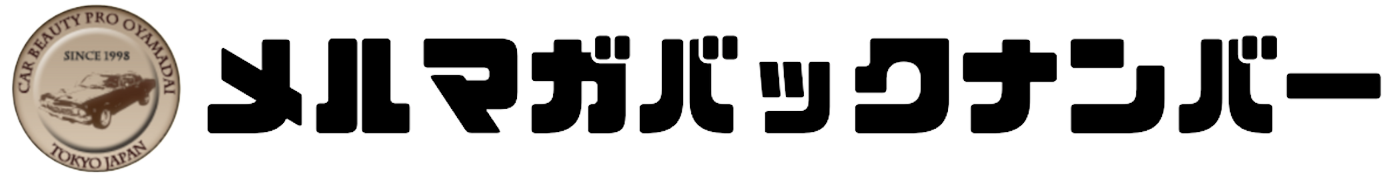
コメント