今日のお話です
どうぞご覧ください
気付かずうちに囲まれている その2
昨日の続きです
AIが身近になったのは
1990年代後半に検索エンジンが登場し
日本でもカーナビに音声認識が
搭載され始めた頃でしょう
その後、2010年代になると
スマートフォンの普及によって
AIは一般の人々の生活に一気に浸透します
ここで少し歴史を振り返ってみましょう
実は、AIの歴史はもっと古く
その始まりは1950年代にさかのぼります
英国の数学者アラン・チューリングが
「機械は思考できるか?」という
素朴な疑問から始まり
1956年のダートマス会議では初めて
「Artificial Intelligence(AI)」という
言葉が使われました
当初の研究は
チェスを指すプログラムや
数式を解くシステムなど
「人間の推論を真似る」試みから
スタートしました
ですが、AIの歴史は
順調だったわけではなく
盛り上がりと停滞を
何度も繰り返してきました
これ以後の歴史を簡単にたどると
1960〜70年代
推論や探索のプログラムが登場し
期待されるも
コンピュータ性能が追いつかず停滞
1980年代
知識をルール化する
「エキスパートシステム」が
流行しましたがルールの追加や維持に
膨大なコストがかかり
勢いは続かず再び停滞
1990〜2000年代
統計や数学を応用した機械学習が進展
機械学習とは
大量のデータを学習させ
AIが自らパターンを発見する仕組みです
そして1997年にはIBMの「Deep Blue」が
チェス世界王者カスパロフに勝利し
AIの可能性が現実的になりました
さらに、インターネット普及で
データ量が爆発的に増え
この後のAI進化の土台となります
ここで思い出すのが
友人が初めてカーナビの音声認識を
使ったときの様子です
カーナビに向かって
「大きな声で」
「いつもより滑舌を良くして」
「前のめりになり」
「ゆっくり」と話しかけていました
その姿を見て、私は笑いをこらえながら
「まさにこれが、人間が初めて
テクノロジーに触れるときの
純粋な姿なんだ」と…
友人には申し訳ないのですが
思い出すたびに
また、つい笑ってしまいます
長くなりましたので続きは次回に
次回は「現代から未来へ」
そして「シンギュラリティは
いつ訪れるのか?」
という話題でいこうかなと思っています
参考文献・資料
・ダートマス会議(1956年)
AI研究の起点とされる国際会議
・IBM「Deep Blue」チェスマッチ(1997年)
当時の世界的ニュース
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
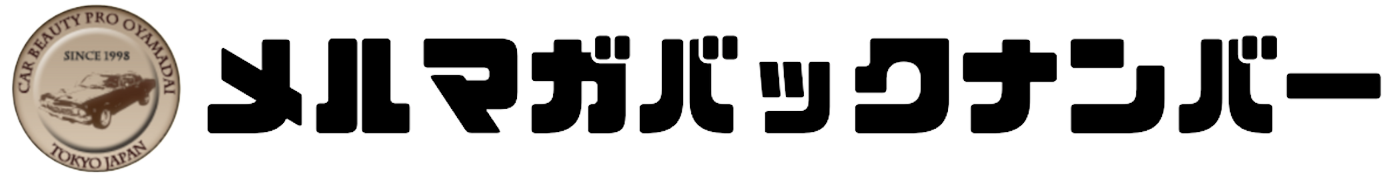
コメント