今日のお話です
どうぞご覧ください
電気に生かされる私たち その5
ギルバートが電気と磁気を整理し
ようやく“電気”が科学の言葉になってから
静電気の研究は一気に加速していきます
そのきっかけとなったのが
1663年に 世界初の摩擦起電器 を
発明したドイツの科学者
オットー・フォン・ゲーリケ でした
琥珀をこすって得られる
わずかな静電気とは違い
ゲーリケは巨大な硫黄の球を回転させ
“人工的に電気を作り出す”ことに成功します
この装置は1706年
イギリスのホークスビーらによって改良され
さらに強い電気を
発生させられるようになりました
また、当時の科学者たちは
電気を生活に使う未来なんて
まだ想像すらしていません
静電気で何かを動かしたり
照らしたりする技術は存在しておらず
起電器はあくまで
自然界の謎を解くための装置 でした
とくに彼らが追い求めていたのは
“雷の正体” です
なぜ雷はまぶしく光るのか?
なぜ火花が飛ぶのか?
人間に害があるのか?
雷と琥珀の静電気は似ているのか?
これらを比較するために
人間が人工的に電気を作る必要があったのです
さらに当時は
電気は流れるのか?
力はどれほどか?
物にどう作用するのか?
すべてが未知でした
摩擦起電器で実験を重ねるうちに
電気が 火花・光・衝撃 などの
性質を持つことが少しずつ明らかになり
人類は“人工の雷”を手に入れます
この小さな火花が
やがて 「雷は電気である」 という
大発見へとつながっていきます
一方その頃、日本は江戸時代
武士階級・城下町・農村社会が安定し
「陰陽道」「儒教」「仏道」
による世界観が主流で
ヨーロッパで起きていた“電気の実験”などは
まだほとんど伝わっていませんでした
それでも江戸の町は驚異的に発展し
人口100万〜120万人の
“世界最大級のメガシティ” に成長します
将軍の城下町として
浅草・日本橋の巨大商業圏
全国から物資が集まる流通網
整備された水道と治安システムと
電気の存在すら知らなかったのに
都市としてこれほど機能していたことは
逆、凄いですね
出典:参考
Otto von Guericke
「1663年に世界初の摩擦起電器を発明」について
Francis Hauksbee
「1706年に電気発生装置を改良」について
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
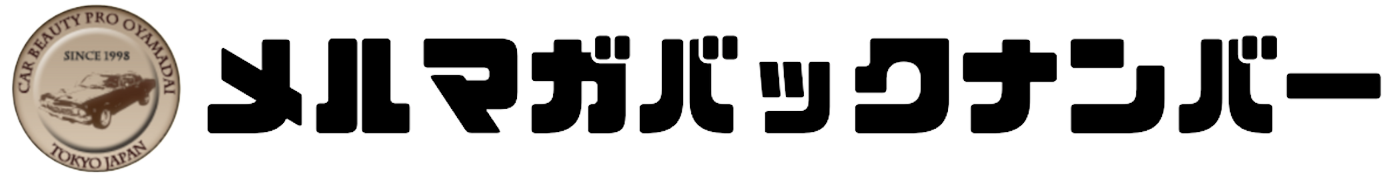
コメント