今日のお話です
どうぞご覧ください
火縄銃の尾栓からISOねじまで
日本は戦後の混乱を乗り越え
その後、産業は高度経済成長へと進みます
急速な経済成長の中で
「国際的に通用するねじ規格」を
整える必要に迫られ
その中心となったのが
JIS(日本工業規格) です
当時はアメリカの UNC/UNF(インチ系)と
国際標準化機構 ISO の メートルねじ を
併用する「二重体系」でしたが
1960年代に入ると国際取引の増加により
JIS=ISO整合化 が国家方針として進められます
1961年、日本はISO(国際標準化機構)の
正会員として正式加盟
同年、JIS B 0205(メートルねじ)が
ISO 68 に整合化され世界標準と完全に一致する
Mねじが国内産業に広く浸透していきました
この改訂によりJISねじは
ISOメートルねじと完全互換となり
「世界どこでも使える日本製品」の
基礎がここに築かれたのです
そして1966年
トヨタ・カローラ(KE10型) が登場
JIS・ISO準拠のメートルねじ体系で
完全設計された日本初の量産乗用車でした
同年、日産サニー(B10型)も
同規格で設計され
「JISとISOが生んだ国産車」といえる存在です
これにより、自動車産業を筆頭に
造船、鉄道、航空機、精密機械など
あらゆる分野が統一された
ねじ体系のもとで発展し
1970年代には
JISとISOの差異がさらに統合され1981年に
JIS B 0205(ISO 68完全整合版) が制定
ここでようやく日本のねじ規格は
世界と同一基準となりました
さらに1987〜1989年にかけて
日本はISOとの整合を一層進め
JIS B 0205(メートルねじ) が
ISO 68/ISO 965 と完全統一し
1989年以降の日本製ねじは
ISO規格と完全互換を持ち
日本国内で製造されたボルトやナットが
そのまま欧州製品や航空機規格にも
適合するようになりました
この「国際統一化」が
日本の精密工業(特にカメラ・自動車・電子部品分野)の
輸出競争力を飛躍的に高めたのです
そして、国内のねじメーカーが
世界共通ねじを製造できる国となったのは
1543年、火縄銃の尾栓に
初めて「ねじ」を見たその日から
実に約446年後のこと でした
10月1日から
「ねじ」のお話にお付き合い頂き
ありがとうございます
この約446年の間に積み重ねられた
技術者たちの知恵、技術、そして努力は
ほんの一部分で
わずか11日間では語り尽くすことはできません
でも、こうして私たちが
何も考えずに工具を手に取り
当たり前のように「ねじを回している」こと
そのすべての「当たり前」は
誰かの努力と時間の上に
成り立っているのです
出典・参考文献
日本産業規格(JIS B 0205:1961・1981・1989版)
日本産業標準調査会(JISC)
ISO 68, ISO 965(国際標準化機構)
工業技術院
『日本工業規格の沿革と国際整合化』(通産省, 1989)
日本ねじ工業協会『ねじ技術史年表』(1997)
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
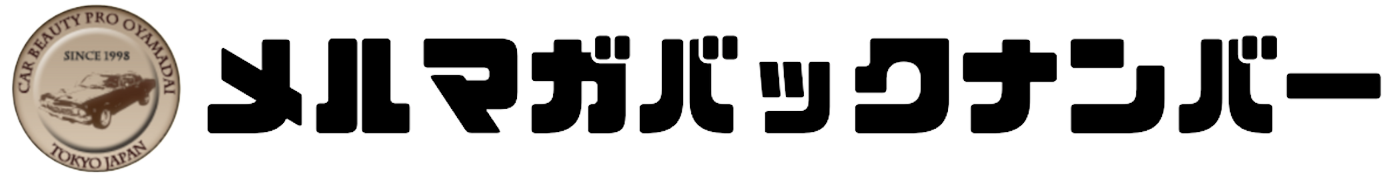
コメント