今日のお話です
どうぞご覧ください
日本のねじはどこへ向かうのか?
1917年に国家規格「JES(日本標準規格)」が
制定されここから
「国産ねじ」の時代が始まりました
当時は第一次世界大戦の真っ只
中日本は連合国側として参戦しましたが
主戦場はヨーロッパであり
日本国内の軍需生産はまだ小規模でした
そのため日本はイギリス・フランス・ドイツなどから
戦車・航空機・火砲といった兵器を輸入し
一部を分解して研究、模倣していました
が
しかし、ここで問題が起こります
イギリス製兵器はウィットウォースねじ
フランス製兵器はフランス式メートルねじ
ドイツ製兵器はドイツ式メートルねじ
同じ「メートルねじ」であっても
フランス式とドイツ式では
ピッチや公差が微妙に異なり
互換性が取れなかったのです
結果として、国ごとに異なるねじ規格が混在し
補給、修理のたびに現場は大混乱に
それでも、日本の職人たちは
手ヤスリや旋盤を駆使し
現物から逆算してねじ山を再現
ねじの頭を切ってJESねじを溶接し直すなど
なんと、「現物合わせ」でねじを製作して
対応していました
「規格がなくとも仕上げる」
当時の職人たちの底力を感じますね
第一次世界大戦での経験は
日本の工業界にとって大きな教訓となりました
国ごとに規格が違えば
ねじひとつまともに合わず、修理も補給も滞る
この「ねじ地獄」は
二度と繰り返してはならないと
そこで日本は1917年に制定した
JESを基礎により精密で産業横断的な
標準化を進めていきます
そして1931年航空機産業が急速に発展し
ねじの精度が厳しく求められる時代を迎えます
このとき制定されたのが
航空機、兵器用ねじ規格
「JES-Aシリーズ」でした
しかしJES-Aはイギリスのウィットウォース系ねじ(BSW)を
基礎としたもので寸法体系はインチで設計された
日本独自の航空、兵器用規格でした
この統一規格の採用により日本の航空、軍需産業は
一気に標準化へと進みます
1933年
川崎航空機工業株式会社による
陸軍 九一式戦闘機
中島飛行機株式会社による
海軍 九〇式艦上戦闘機 が量産化
これらの機体には、JES-A規格(インチ系) の
ボルト・ナットが使用されました
1935年
三菱航空機株式会社の 九六式艦上戦闘機
三菱内燃機製作所(後の三菱重工業)の
九五式軽戦車 が登場
この時点でも
機体・砲塔・駆動系・操縦系など
主要構造部のねじはすべて
ウィットウォース系インチねじが主流でした
1937年
日中戦争の開戦を機に
軍需生産が急拡大しねじの標準化が国家として
避けて通れない課題となります
しかしその一方で
1938年以降、ドイツとの軍事技術提携が始まり
航空機・兵器分野を中心に
ドイツ工業規格(DIN) に基づく
メートルねじ(DINメートル) が
導入され始めました
これにより、日本国内の軍需工場では
ウィットウォース(インチ)と
ドイツ式メートル(DIN)の両方が並存し
そして1939年
ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発
その頃の日本では
陸軍がメートル(DIN系)
海軍がインチ(JES-A系) という、
前代未聞の「ねじ二重構造」に
突入していったのです
ドイツ式メートルが流入し始めても
依然として日本の主体は J
JES-A(インチ系) にありました
このあと、日本はどのように
ねじ規格の戦いを乗り越え
戦後のJIS・ISOへと辿り着いたのか・・・
つづく
昨日、「次回でまとめます」と書きながら
あまりに変化の多い時代だったため
気づけばもう少し深掘りしていました
明日か明後日には
さすがにまとまりそうです……
出典・参考文献
日本工業標準調査会
「JISの歩み ― 日本標準規格(JES)からJISへ」
科学技術庁『日本工業標準化史(1955)』
JIS B 0206・JIS B 0207
(メートルねじ・インチねじの基準)
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
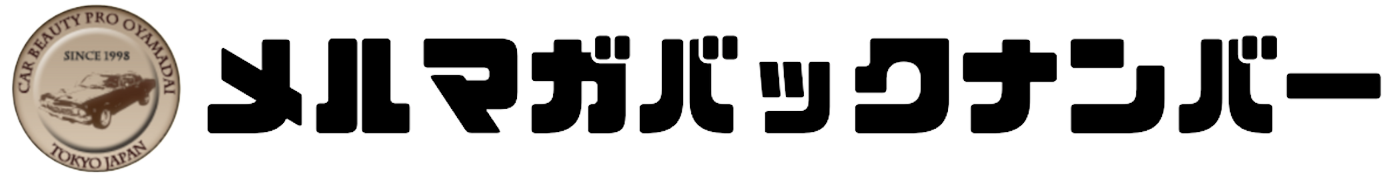
コメント