今日のお話です
どうぞご覧ください
手作業から機械へ
日本人が初めて目にした
「ねじ付きの金属製品」から6年後
1549年、鹿児島に上陸した
イエズス会の宣教師 フランシスコ・ザビエル
皆様もご存じのとおり
日本にキリスト教を伝えたことで
知られていますが
彼が持ち込んだのは宗教だけではありません
時計・眼鏡・薬研(やげん)など
精密ねじを用いた器械類も持ち込みました
それがのちの「南蛮時計」の原型となり
日本人が初めて「精密ねじ」という技術に
触れた瞬間でもありました
そして次に、長崎出島に来日したドイツ人医師
フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト
およびオランダ医師
ヤン・カレル・ファン・デン・ブルックが
それまで「道具」として伝わっていた
「ねじを使う精密器械の文化」を
「技術」として日本に伝えたのです
1823年、シーボルトは
顕微鏡・時計・測量機器・地球儀など
いずれも精密ねじを用いた
科学機器を持ち込みました
特に外科器具や顕微鏡には
金属ねじによる微調整機構が備わっており
日本人は初めて「ねじで精度を出す」
という考えに触れました
さらに1849年オランダ国王の命を受けて来日した
医師ヤン・カレル・ファン・デン・ブルックは
医学のみならず物理・化学・工学にも精通し
出島で日本人に金属加工や旋盤理論を教授しました
彼が持ち込んだのは手動金属旋盤・ボール盤・タップ
ダイス・精密測定器など当時としては最先端の
「ねじを作るための道具」でした
そして1854年オランダ軍艦 ソーランド号 が
長崎に来航し艦内の修理工場を日本人技術者に公開します
そこにあったのは鉄を削り、ねじ山を刻み
軸を精密に仕上げる金属旋盤
これを目にした佐賀藩は
その構造を徹底的に観察しわずか3年後の
1857年技術者 田中久重 が中心となって
木製ベッドに鉄製主軸を組み合わせた
国産旋盤を完成させました
この旋盤は砲身や機械部品の加工に使用され
まさに「日本が初めて自らの手で
ねじを削り出した瞬間」でしたが
佐賀藩の旋盤は
「ねじを削る」構造を持ちながらも
主に試作や研究の段階にとどまりました
さらに同年
長崎製鉄所(後の三菱長崎造船所)では
オランダ人技師 ファン・ドールン の指導で
イギリス製の旋盤が導入され
その旋盤は歯車付きの送りねじを備え
実際にボルトやナットを削り出せる
日本初の実用的旋盤でした
そして日本国内には
佐賀藩製の国産旋盤と
幕府が長崎製鉄所に導入した
オランダ製旋盤が並びました
ここで気になるのは
その旋盤で削り出した
「ねじの規格」ですね
続きは明日に
要点を抜粋して紹介しましたので
詳しい内容は、下記の資料をご確認ください
出典・参考文献
「日本科学技術史大系 機械篇」(日本科学史学会)
「シーボルト日本」(講談社学術文庫)
「出島日記」(ヤン・カレル・ファン・デン・ブルック 著)
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
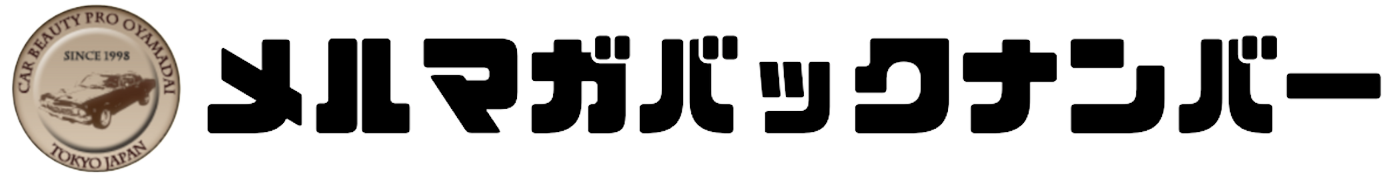
コメント